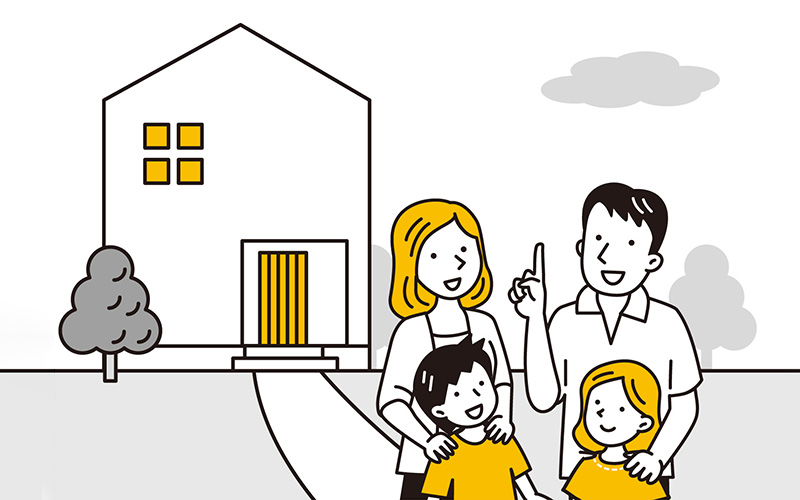臭いの秘密~フィトンチッド2
2007.04.16 Mon
おかまっぷです。
今回はフィトンチッドのお話のつづきです。
二次的に生産されるこれらの化学成分のうち、主要成分は、いずれの樹木にも含まれておりその構成比率も樹種による差はほとんどありませんが、微量成分の種類と含有量は、樹種によって大きく異なります。成分によっては、特定の樹木にしか含まれないものもあります。
たとえば『ヒノキチオール』は、ヒノキに含まれる成分と誤解されることが多いのですが、日本のヒノキには含まれていません。タイワンヒノキ、青森ヒバ、能登ヒバなどに含有されている成分です。同じヒノキ科でもこのような違いがあります。
ちなみに上記の誤解はその発見と命名とに由来しています。ヒノキチオールを発見して命名したのは、野副 鐵男氏(東北大学名誉教授、故人)です。同氏は、1926年から1948年までの22年間にわたり、台湾総督府専売局、台湾総督府中央研究所、台北帝国大学において、台湾産の動植物成分の研究に携わっており、その研究の一つが『タイワンヒノキの精油成分の研究』だったのです。この研究成果は1936年の日本化学会誌に発表されました。このように、微量成分としてのフィトンチッドは樹種により大きな差異が見られます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【補足説明】
上記では、『ヒノキチオールは、日本のヒノキには含まれていない』としましたが、これについて若干の補足説明をします。ヒノキチオールは、上記のように、タイワンヒノキから最初に単離された物質です。その後、日本産ヒノキにも含有されているかどうか研究されましたが、現在までにその存在は明確に証明されていません。しかし、最近になって、『微量ではあるが含まれている』とした報告も出ています。たとえば、第50回日本木材学会大会において、岐阜県森林科学研究所の森氏、森林総合研究所の大平氏、同研究所の松井氏、の研究グループは、『ヒノキ材からのヒノキチオールの検出について』を発表しました。その中で、『ヒノキ材抽出物のTMS誘導体のGC/MS分析の結果、ヒノキチオール(-ツヤプリシン)由来のピークが検出され、さらに異性体である・及び・ツヤプリシン、類縁体である
・ドラブリンもあわせて検出された。』と報告しています。簡単には検出できないほどの微量ながら、今まで疑問視されてきたヒノキチオール存在の可能性が示唆されたわけです。これは、分析機器と分析技術のめざましい発達によって、従来は難しかった化学物質の検出が、容易に行えるようになってきたからだと思います。
今後、実際にヒノキチオールが単離されれば、その存在が証明されることになり、上記の『ヒノキチオールは、日本のヒノキには含まれていない』は、現時点での話であって、近い将来訂正しなければならないかもしれません。