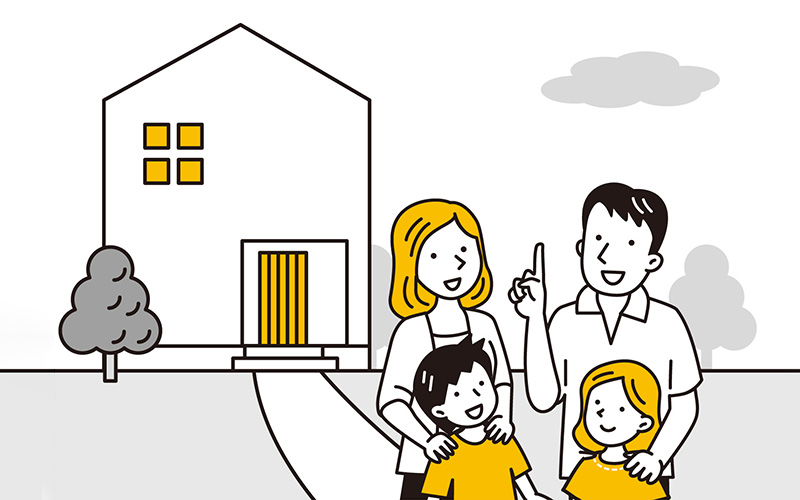京の町家から学ぶ
2015.01.25 Sun
こんにちは、ICの小林です。
年末年始に京都に行ってきました。
今回の目的は、
「照明を観に行くこと」と「京町家にお邪魔すること」。
今日は、町家のご紹介をします。
京都に行くと町のあちらこちらに見かける「町家」。
古都としての景観を守るべく、
京都市内は厳しい建築規制が敷かれています。
今回は、観光用の町家というよりは、
実際に町家にお住まいになっている方のお家を訪問見学しました。

京都の町家は住居と店舗が一体となった住居形式がほとんどです。
特長的なのは、通りに面している玄関の間口が狭く、
奥行きが深く長い敷地がほとんどで
この長方形に整備された敷地群の形成が「一条、二条、三条」といった
碁盤の目通りの街並みを形成しています。
通りに近い方から店舗、茶の間、居間、座敷、
と奥に行くほど居住空間が広がり
通り庭とよばれる土間空間が細長い建物を
渡り廊下のように通っています。
奥には奥庭や蔵、離れがあります。
改めて驚いたのが、長い歴史の中で必要に応じて
増築改築を繰り返しており、
もともと庭だったところに部屋を次々と増築し
各部屋に移動するごとに微妙な段差がうまれています。
そして、関東の畳と京都の畳は大きさが違うので
畳一畳が広々と見え3畳の茶の間空間でもゆったり過ごせました。
今の住宅のように、照明は明るくはありませんが、
店舗の一部の天井は瓦をぬき天窓のガラスがはめ込まれ
今でいうトップライトから一定の光量が
入り作業がしやすく工夫されていたり
夏はブラウン系の御座を畳の上にひいて薄暗くし、
冬場は障子紙や畳の色で部屋を明るく暖かくみせたりと
必要なところに必要な明るさ、温度感覚をコントロールしたりと
工夫がいっぱいありました。
奥庭は、昔は周辺の家々が、奥庭が一カ所に集まるように
設計されていたようです。つまり、垣根はあるものの、
2~4軒分のガーデニングエリアが隣り合っており
ウグイスが来訪するようなこともあったそうです。
今は、隣にマンションが建ってしまい、鳥もこなくなってしまったとか。
1000年続いた都の古き良き伝統の家屋・・と言いたいところですが
京都はその歴史の中で何度か内戦や大火に見舞われ
その都度町を再建しています。
このお宅はなんと蛤御門の変(1788年)という
市街地一体が焼失した大火災で住居兼店舗が焼かれ、
その際に貴重品である、桜の木でできた分厚い店看板を
井戸に投げ込んで消失をまぬがれたという歴史があります。
1788年といえば・・227年前です!
ざっくり考えても、227年前以上から
このお家はここで生業を立てていたのですね。

昔の人たちの暮らしぶりや
先人の知恵にいたく感動した、京都でのひと時でした。