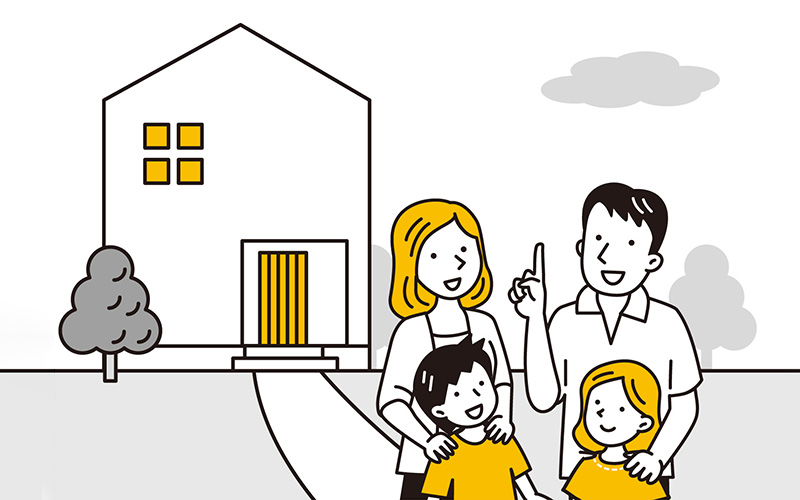住宅に使われる光源(1)
2006.07.29 Sat
こんにちは!お久しぶりです、こいけっちです。
今回は、住宅で使われる光源の知っていそうで知らない、いまさら人には聞けないお話をしようと思います。
住宅で主に使われている光源とは、みなさんもご承知のとおり白熱灯と蛍光灯です。みなさんはこの二つの違いがお分かりですか?
以外にも、知らない方が結構いらっしゃいます。それぞれの、特徴をしっかり掴み、その適正にあった場所に光源を配置すれば、電気代の節約にもなりますので、どうぞ参考にしてみて下さい。
【白熱灯の構造】
みなさんもご存知の通り、白熱灯は「フィラメント」と呼ばれる真ん中のコイル状の金属に電気を流すと「フィラメント」の電気抵抗で
熱され、白熱化して赤白色に輝くしくみです。
そのサイズは口金の直径で表します。(例:サイズE26=直径26㎜の口金)

【蛍光灯の構造】
蛍光灯は白熱灯とは違い、放電現象によって点灯しますが、放電は本来不安定なものなので、蛍光管自体だけでは点灯出来ません。
安定器や点灯管があって始めて点灯します。
蛍光管の中には「フィラメント」と「水銀原子」があり管のガラス部分の内側には蛍光塗料が塗ってあります。
まず、電圧をかけると「フィラメント」から電子が飛び出し放電が始まります。
飛び出した電子と水銀がぶつかり紫外線が発生します。
その紫外線が蛍光物質(蛍光塗料)に当たり、可視光(目に見える光)にかわるのです。
※蛍光灯の光色は、蛍光管の内面に塗付されている蛍光塗料の種類できまります。
【電球型蛍光灯の構造】
蛍光灯と同様に、水銀蒸気中の放電によって紫外線を発生させ、この紫外線による蛍光物質の発光を利用しています。
(2)へ続く